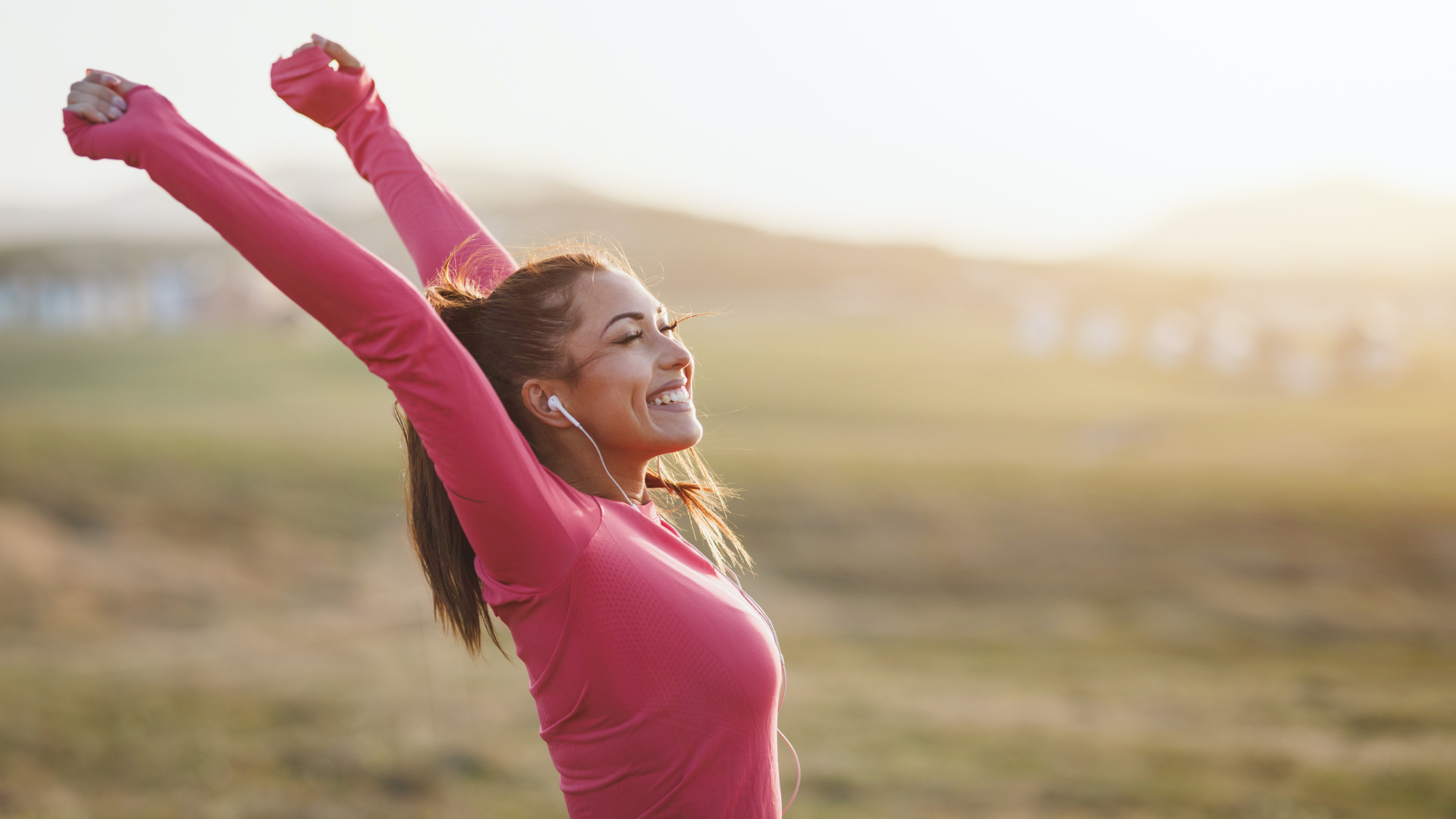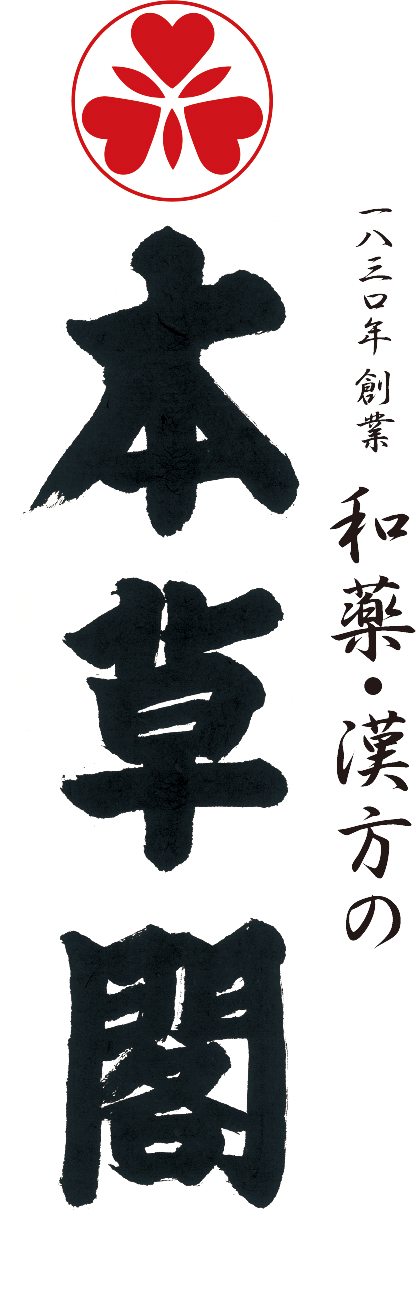漢方で「気」を知ろう2025年10月21日
「気」を整えよう

漢方では、健康のカギを握るものとして「気・血・水」という3つの要素が重視されます。
これらがバランスを取りながらしっかり巡っているとき、人は心身ともに調子がよく過ごせると考えられます。
本シリーズでは、「気・血・水」の第一弾として「気」をテーマに、気が不足したり滞ったりしたときの症状、原因、そして日常でできるケア(漢方・養生)を紹介していきます。
「気」とは?
漢方でいう「気」は、生命のエネルギーとして例えられ、見えないものですが、体を動かす力、呼吸・消化・代謝などを支えています。
気にも種類があり、
・先天の気:親から受け継ぐもの
・後天の気:飲食・呼吸・日常生活で作られるもの
とされ、後天の気を補うことが日ごろの養生で重視されます。
「気」の不調で現れる3つのタイプ
気のバランスが乱れると、次のような状態になります。
①気虚(ききょ)
気が不足している状態。
症状→疲れやすい、無気力、体がだるい、食欲不振、風邪をひきやすいなど。
②気滞(きたい)
気の巡りが悪くなり滞ってしまう状態。
症状→イライラ、ため息が多い、胸や腹の張り、喉の詰まり感など。
③気逆(きぎゃく)
気の流れが乱れて上へ逆上してしまう状態。
症状→のぼせ・動悸・頭痛・吐き気・顔のほてりなど、上部の異常。
気の不調はこれら一つだけで出ることもありますし、複数が重なって現れることもあります。
気の不調を生む原因・きっかけ
気が乱れる理由はひとりひとり異なりますが、以下のような要因がよく関係しています。
①食生活の乱れ
食べ過ぎ、消化不良、偏食などで後天の気がうまく生み出されない。
②過労・慢性疲労
休息不足・慢性的なストレスで気の消耗が進む。
③感情の起伏・ストレス
怒り・憂鬱・抑うつ・イライラなどが気の巡りを妨げる。
④気候・気圧の変化
湿気・寒暖差などが気の巡りを妨げることもある。
⑤運動不足・血流低下
血の巡りが滞ることで気の巡行にも影響を与える。
不調が続くと、気の乱れは他の「血」「水」の不調にも波及することが多く、早めに対処することが大切です。
日常でできるケア(養生・漢方)
日常でできる養生について紹介していきます。
・バランスのよい食事
気が不足している方 ⇒ 芋類、豆類、適量のタンパク質(お魚・お肉)、黒人参
気の巡りが悪い方 ⇒ 香りのもの(紫蘇・薄荷)、玉ねぎ、ピーマン、柑橘類
以下の習慣は、すべての「気」の不調に有効です。
・適度な運動
軽いストレッチやウォーキングで巡りを促す。
・呼吸・リラックス
ゆっくり深呼吸、腹式呼吸、瞑想や軽いヨガなど。
・十分な休息・睡眠
回復の時間を確保する。
十分な睡眠時間の確保はもちろん大切ですが、睡眠の質も「気」の不調の改善には重要な要素です。
睡眠の質を向上させるために、寝る前のリラックスタイムを意識して、気持ちよく眠れる環境を整えましょう。
・ストレス管理
趣味や気分転換、感情をため込まない習慣をつくる。
・暑さ・寒さ対策
体が冷えないように腰・お腹・足元を温めるなど。
気の不調がある方の漢方薬を紹介していきます。
以下紹介する漢方薬はよく使用されるものですが、ひとりひとりの体質に合わせて選ぶ必要があります。
①補中益気湯、六君子湯
疲れやすく、胃腸の働きが落ちている方に。
体の気を補い、脾(胃腸)の働きを助けます。
②半夏厚朴湯、香蘇散
気の巡りを良くして、張りや不快感を軽減します。
③加味逍遥散
気の滞りやのぼせを鎮めるよう気の巡りを調整します。
ここでおすすめの生薬は、高麗人参です。
高麗人参は、「気」を補い、身体のエネルギーを底から支える代表的な生薬です。
疲れやすい方や、眠りの浅い方の体力回復にも役立ちます。
黒人参は、高麗人参をさらに熟成させたもので、「気」だけでなく「血」の巡りも整え、眠りの質を高めたいときにおすすめです。
気を整えるとどうなる?
気が適切に巡る・不足が補われると、以下のような変化が期待できます。
・活力・やる気・集中力が改善
・消化吸収・代謝の改善
・不快な張り感・不定愁訴・イライラ感の緩和
・他の不調(血・水)にも良い影響
また、気を整えることは「未病(発症する前の不調)」対策としてもとても重要です。